育休取得はパパにとって、子育てに専念するだけでなく、自分自身の成長や夢を掴むことができる貴重な時間です。
職場の事情や待遇が気になる方、兄弟が保育所に通えなくなる場合もあるかもしれません。また、毎日が休日になると出費も増えがちで、無駄遣いが増えてしまうかもしれません。
そこで、産後パパ休暇を1ヶ月取得し、現在は9ヶ月の長期育休中の筆者が、育休取得前に知っておくべきことをまとめました。
具体的には、夢を持つことで自分自身を成長させる方法や、節約生活を送るためのコツ、育休明けに備えるためのコミュニティ構築などを解説しています。
この記事を読むことで、育休中に無駄な時間を過ごさず、自分自身を成長させる有意義な時間にすることができます。
給与には注意が必要!育休開始は 給与事情を調べてから
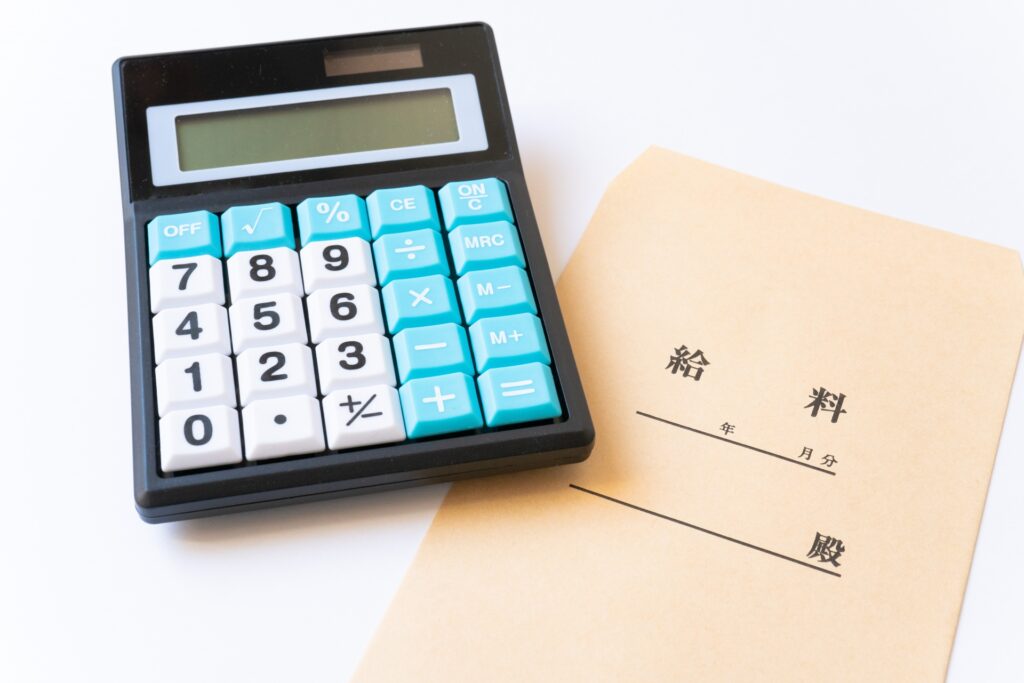
育児休業を取得する際には、給与面に注意が必要です。
これまで楽しみだった給料日も、育休中は住民税やその他雑費だけが差し引かれる怖い日となってしまうからです。
財形貯蓄など職場で天引きされる貯蓄や中止できる積立は、事前に止めることで毎月の給与減額を抑えることができます。
また、最終月の給与は過払いにより返金を求められることがあります。
わたしは事前通告なく、翌月給料日に返金を求められました。
会社の給与計算方法を調べて、育休開始日を決めましょう。月の途中から育児休業を取得する場合には、有給休暇を活用することで給与の減額を阻止することができます。
実際に体験した実例。
・1月15日まで働いており、1月25日の給料日には全額振り込まれる。
・1月16日から育休に入り、8月31日まで育休を取得する。
・育休中は給料が支払われないため、過払いが発生。
・翌月の給料日に過払い金の返金が求められる。
この場合、1月15日まで働いていた分の給与は通常に支払われますが、1月16日からの育休分については過払いが発生します。 つまり、1月25日の給与日には、育休分に相当する過払い分が含まれてしまいます。
そのため、翌月の給料日には過払い分を返金することになります。 具体的には、2月25日の給料日に、1月16日から31日までの育休分に相当する過払い金が給与から減額されるということになります。
実際は、振り込まれる給料がないので、過払い分を病院の口座に振り込みました。金額にして25万円。育休中にはとても大きな金額でした。
但し、返金に関する詳細は、会社の制度やルールによって異なる場合があります。 そのため、具体的な詳細については、会社の担当者や払込担当者に確認することが必要です。
月の途中の育休開始の場合、事前に総務課などに伝えておくと回避できるかもしれません。
このように、育児休業を取得する際には、給与面についても考えることが大切です。育休を取得することで、収入が減ることは避けられませんが、上手に対処することで、収入面での安心感を得ることができます。
育休明けの職場復帰が不安!事前のコミュニティ構築が大切

育休明けになると、職場の事情や待遇が変わります。 例えば、配属先が変更になる場合や、仕事内容が変化する場合もあります。
育休明けに不安があるとすれば、このような職場事情に関してではないでしょうか。 そのため、育休明けには事前に職場や通園先などに確認することが大切です。
具体的には、職場で仲の良い友人や知人とSNSを通じて繋がったり、同じように出産や育児を経験したパパやママとコミュニティを作ったりすることがおすすめです。
私の勤務する病院では、育休明けの配属先は不明です。これまでの所属先の手術室師長ではなく、看護部長が決定するということでした。 そのため、配属先や仕事内容について事前に希望を伝えるだけでも、少しは不安が紛れそうです。
育休取得後の会社の待遇の変化、復帰後の職場環境について情報を持っている場合には、自ら周囲に共有することで、同じように不安を抱えている人の参考になるかもしれません。自分から情報発信をすることも大切にしていきましょう。
育児と仕事の両立は大変です。事前にコミュニティを構築し、育休中から情報収集し、周囲とのコミュニケーションを密にすることで、スムーズな職場復帰ができるはずです。
兄弟が保育所に通えない?市町村や保育所に確認しよう

育休中は、兄弟が保育所に通えなくなる場合があります。 特に、両親が同時に育休を取得する場合は注意が必要です。 これは、市町村によって異なるため、事前に確認することが重要です。
わが家では、奥さんの育休取得で時短保育になりました。さらにパパである筆者も育休取得すると、保育所と市役所で協議することになりました。いま現在、協議結果は出ていません。
兄弟の通園が拒否された場合、保育園料は浮くものの、子供たちを自宅で見ることになるため、育休自体が台無しになる可能性があります。「育休を取らないで、仕事をしてた方が自分の時間や気持ち的な余裕があるため、育休を取るよりも楽だ」という意見もあります。
しかし、子育てに専念することができる貴重な時間である育休期間を活かすことができるよう、市町村や通園先に確認しておくことをおすすめします。
育児と仕事の両立は大変なことです。育休取得期間によっても対応が変化することがあります。事前に市町村や保育所に確認することで、スムーズな育休生活が送れるようになります。
毎日が休日でも無駄にしないで!節約生活で賢く過ごすコツ
毎日が休日になると出費も増えがち

育休中は毎日が休日となり、外食や外出などの出費が増えてしまいがちです。無計画にお金を使ってしまうと、後になって大きな負担になってしまいますそこで、計画的な節約生活を送ることが大切です。
計画的に節約生活をすることで、貯蓄を切り崩さない
育休中は収入が減ってしまうため、貯蓄を切り崩さないことが重要です。例えば、家で料理をすることや、必要なもの以外は買わないようにすることが大切です。また、育休中に不要なものを売って収入を得る方法もあります。
わが家では食材は配送を利用しています。これまではOisixを利用していました。子供が生まれたあとは、手数料・配送料が1年無料(赤ちゃん割引)のCOOPに変更しました。離乳食も豊富で、安くて便利。
食材配送を利用するのは、夫婦ふたりで夢を追いかけていて、時間が惜しいからです。実際はスーパーに買い出しに行って、献立を組んで、自炊し続けるのが1番の節約です。こればかりは、家族のスタイルで検討ですね。
平日に外出や外食をすることで、お得に楽しめる場所を探そう
育休中は、働いている人とは逆の思考パターン「土日祝日は出かけず、平日に外出や外食を楽しむ」という考え方に変化します。泣いたり、騒ぐ子供を連れているので、少しでも空いているときを選びます。節約志向になっているので、少しでも安い日にちや時間を選びます。その結果が平日のおでかけです。
育休中は時間があるので、様々な情報を収集し、お得な情報を見つけることができます。親子で楽しめる無料イベントもありますので、調べてみるといいでしょう。
育休中の夢を持つ!挑戦することでより有意義な時間に

育休中は、子育てに集中することも重要ですが、自分自身の成長や夢を掴むこともできる貴重な時間です。具体的な目標を持って、挑戦することで、より有意義な時間を過ごすことができます。
自分が興味を持っている分野や、今までやってみたかったことなど、さまざまな夢があるでしょう。 目標を設定することで、自分自身の成長や、将来のキャリアアップにもつながるかもしれません。
次に、具体的な行動計画を立てましょう。目標を達成するためには、それに向けた取り組みが必要です。例えば、自分でビジネスを始めるための勉強をする、投資の勉強をする、語学を学ぶなど、挑戦することはたくさんあります。取り組むことができれば、自信にもつながります。
わが家では奥さんが、初回の育休で起業塾に参加。自身の強みを分析したり、ビジネス開始に向けて勉強をしていました。そして、今回の3回目の育休で副業物販に初挑戦。売上を毎月伸ばしています。
育休明けには副業を自動化し、毎月安定した収益を上げることを目標としています。目標に向かって勉強したり挑戦することは、育休中にできる有意義なことのひとつです。
私も育休中に投資の勉強を始め、日本の株式投資に挑戦しています。その経過や学んだことも発信していきたいです。また、以前に挑戦していたブログに再挑戦し、自分の言葉で発信し、見知らぬ誰かに情報提供して役立てるように挑戦を再開し、自信にも繋がっています。
育休中は、自分自身の成長や夢を追いかけることで、有意義な時間を過ごすことができます。 目標を持ち、挑戦することで、仕事とは違う自分自身のスキルを成長させることができるでしょう。
育休中は、家族との時間もたくさんありますが、余暇時間を上手に使って、目標に向けて行動しましょう。
育休明けに向けて、自分自身を成長させる準備をしよう
育休明けには、職場復帰や子育てに向けて準備をする必要があります。 その中でも、自分自身を成長させるための準備も大切です。
自己分析を行い、スキルアップやキャリアアップに必要な知識や技術を身につけるために、書籍やオンライン講座、セミナーなどを活用しましょう。
また、人脈作りも大切な準備のひとつです。 職場や業界の情報を収集するために、同じ分野の人たちと交流を深めることが必要です。 。
さらに、育休中にはじめた副業や趣味を活かすこともできます。自分が得意な分野や興味がある分野で、アルバイトやボランティアをすることで、新しい人脈やスキルを身につけることができます。
育休明けに向けて、新たなチャレンジをすることで成長するための準備をしておきましょう。仕事復帰がスムーズだと子育てにも自信を持てるようになります。
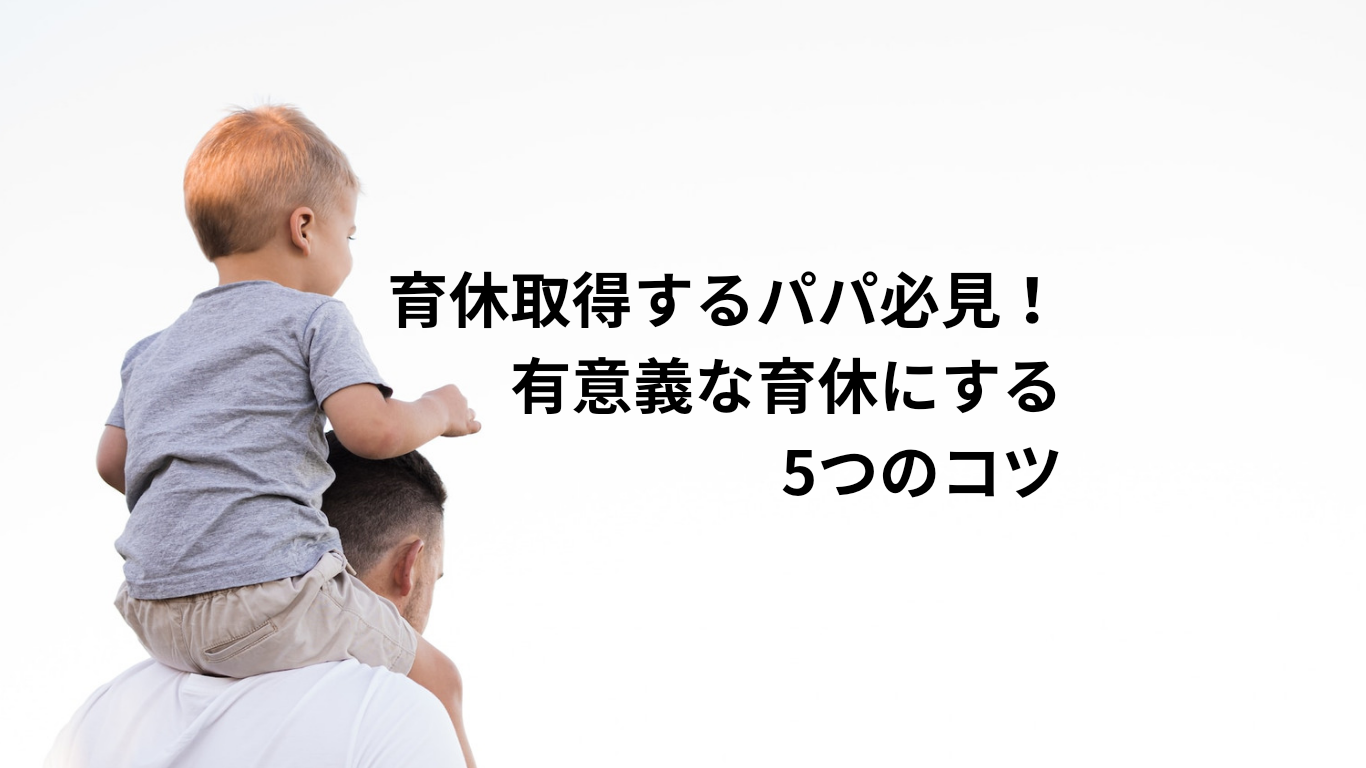
コメント